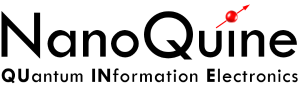┌───\Headline/──────────────────────────
1【機構行事】●6月15日に「量子情報」で第12回PIセミナーを開催します
2【一般公開】●6月8、9の両日、駒場リサーチキャンパス公開が開かれます
3【特論情報】●6月21日に特論・企業集中講義がシャープで行われます
4【周辺情報】●5月23日に光物質ナノ科学研究センター設立記念シンポを開催
5【メディア情報】●機構関係者に関する掲載記事を紹介します
6【会議紹介】●関連会議・行事を紹介します
└───────────────────────────────────
☆★☆記事内容★☆★
┌───────────────────────────────────
1【機構行事】●6月15日に「量子情報」で第12回PIセミナーを開催します
└───────────────────────────────────
★機構は6月15日(金)午後2時半から5時まで駒場リサーチキャンパスAn棟4階
中会議室(An401/402)で、“だれにでもわかる量子情報”をテーマに「第12回
フォトニクス・イノベーション(PI)セミナー」を開催します。講師には東京
大学工学系研究科附属光量子科学研究センター長の小芦雅斗教授と同工学系研
究科古澤研究室の武田俊太郎助教のお二人をお招きします。
通信の安全性を巡っては、現在、量子情報に大きな期待が増しています。量
子暗号通信の中でも、将来的に量子コンピューターによるハッキングにも耐性
を持つ量子ネットワークなどの超高耐性なセキュリティ通信などの研究も進展
しています。一方、量子コンピューターについては、D-Wave社がイジングマシ
ンを商用化して以降、最近では米IBMがクラウド経由でゲート型量子コンピュー
ターにアクセスし、量子アプリケーションの開発促進に供するなど、実用化へ
の動きが活発化し、注目を集めています。こうした中、今回のPIセミナーでは、
小芦教授が「量子鍵配送のセキュリティ:Why and How」と題して、量子暗号
通信の安全性について、武田助教からは「光量子コンピューターの基礎から応
用まで」と題して、光を用い、比較的に大規模化が期待される光量子コンピュ
ーターについて、解説講演がそれぞれ行われます。
PIセミナーは新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)プロジェクト「超低
消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術」(プロジェクトリーダー=
荒川泰彦特任教授)に関わる成果普及と人材育成を目的とした「フォトニクス
・イノベーション協創プログラム(PICC)」に基づいて、社会人、学生向けに、
ナノ量子機構(機構長平川一彦教授)が主催しているセミナーです。
詳細および参加登録については、下記URLをご覧ください。皆様の奮ってのご
参加をお願い致します。
↓↓↓(詳しくは)↓↓↓
http://picc.iis.u-tokyo.ac.jp/eventdetail/photonics-innovation-seminar-12th/
┌──────────────────────────────────
2【一般公開】●6月8、9の両日、駒場リサーチキャンパス公開が開かれます
└──────────────────────────────────
★東京大学駒場リサーチキャンパス公開が今年も6月8日(金)-9日(土)の2
日間、開催されます。機構では、昨年と同様、機構本部があるAs棟1階エレベー
ターホールで展示を行います。特に今年の公開では、機構内に新設した量子イノ
ベーション協創センターの活動を中心に展示する予定です。
同センターは、東大企業ラボ(東大シャープラボ、東大NECラボ、東大日立ラ
ボ、東大富士通ラボ、東大QDLラボ)に、量子ドットラボ(荒川・有田・太田研
究室)を加えた産学連携研究等を推進する組織です。
また駒場リサーチキャンパスの生産技術研究所および先端科学技術研究センタ
ー所属の機構関係教員もそれぞれの居室を中心とした展示を予定しております。
全体の講演会では、岩本敏准教授が9日(土)13時よりAn棟コンベンションホール
において、「光と物質の深い関係~その制御と活用」と題して講演を行います。
日常生活に欠かせない光。その光が物質との相互作用による結果であることをわ
かりやすく解説するとともに、最先端分野への応用まで紹介します。皆様のご来
場をお待ちしております。
↓↓↓(詳しくは)↓↓↓
http://komaba-oh.jp/
┌──────────────────────────────────
3【特論情報】●6月21日に特論・企業集中講義がシャープで行われます
└──────────────────────────────────
★大学院工学系研究科、理学系研究科共通科目の「ナノ量子情報エレクトロニク
ス特論」の今年度最初の企業集中講義が6月21日(木)に、千葉県柏市にあるシャ
ープの材料・エネルギー技術研究所で行われます。当日は13時~13時20分集合、
13時半講義開始の予定です。
講義内容としてシャープの研究開発、同研究所が所在する柏事業所の紹介のほ
か、開発成果の説明やラボツアーも計画されています。
↓↓↓(シャープ柏事業所アクセス)↓↓↓
http://www.sharp.co.jp/corporate/info/base/map/kashiwa.html
┌──────────────────────────────────
4【周辺情報】●5月23日に光物質ナノ科学研究センター設立記念シンポを開催
└──────────────────────────────────
★4月に設立された東京大学生産技術研究所附属光物質ナノ科学研究センター
(NPEM、センター長志村努教授)の設立記念シンポジウムが5月23日(水)15時
から駒場リサーチキャンパスのコンベンションホールで盛況に開催されました。
副センター長の平川一彦教授(ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・機構長)
が前半の司会を務め、まず4月に就任した岸利治生産技術研究所長から「光電子
融合研究センター(CPEC)が改組され、光と物質、エレクトロニクス領域で新た
なナノ科学をキーに他の研究室を後押しするような成果を期待したい」と祝辞を
述べました。またNPEM設置に関わった前生研所長の藤井輝夫大学執行役・副学長
から「キーワードはナノ。ヘテロな学問領域を集めたのはユニークで、大所高所
からの連携に期待したい」と挨拶がありました。志村センター長からは光電子融
合研究センターから発展的にNPEMを設立した経過と全体の概要説明がありました。
とくに「理論分野を含め、新研究テーマ、新分野開拓、新プロジェクトを含め、
研究室連携をより深めていく」と決意が述べられました。
次いで設立記念シンポジウムの目玉となる講演に移り、京都大学高等研究院の北
川進特別教授から「ナノ空間が拓く化学と技術 -PCP/MOF材料の現在と未来-」
と題する記念講演があり、「ガス分離など、メゾスケールの材料科学が重要」と、
様々な可能性に触れました。次いでCPECセンター長でもあった東京大学ナノ量子情
報エレクロニクス研究機構の荒川泰彦特任教授から「量子ドット技術の現状と展望
~産学連携の視点から~」と題する特別講演がありました。まずNPEM設立のお祝
いを述べるとともに、1980年代のエレクトロニクス研究の状況を説き起こしながら、
量子ドットレーザーの提案から国家プロジェクトを介した実用化研究と到達点、そ
して今後、20年後の研究課題までを網羅した講演がありました。
後半の司会を町田友樹教授に交代して、4つのセンター研究分野紹介に移りまし
た。まず志村努教授がナノ光物性研究分野、立間徹教授がナノ光物質研究分野、平
川一彦教授がナノエレクトロニクス研究分野、寒川哲臣客員教授がナノ物質・ナノ
デバイス研究分野についてそれぞれ紹介しました。最後に平川副センター長が閉会
の挨拶として「研究室間の連携を強め、5年後にはセンターの成果といえるように
努力をしていきたい」と決意を述べ、終了しました。
┌──────────────────────────────────
5【メディア情報】●機構関係者に関する掲載記事を紹介します
└──────────────────────────────────
★4月に発足した東京大学生産技術研究所附属光物質ナノ科学研究センターに関し
て、日経産業新聞の先端科学面の企画記事「解剖 先端拠点」で紹介されました。
異分野の研究者が集まり、ナノ領域で光と物質の相互作用を探求し、工学応用を
目指した研究センターで、平川一彦教授のテラヘルツ波を利用したナノデバイス
成果や立間徹教授のナノテクによる高性能太陽電池技術、センター長の志村努教
授の光と物質の干渉縞を利用した次世代メモリー開発などの研究成果が紹介され
ています。
◎日経産業新聞 5月16日付7面 解剖 先端拠点
東大生産研 光物質ナノ科学研究センター
異分野融合で新産業創出
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★慶応大学とIBMは5月17日に横浜市港北区の慶応大学量子コンピューティングセ
ンター内に産学協働組織「IBM Qネットワークハブ」を開設したと発表し、会見に
出席した同大理工学部長の伊藤公平教授の談話などが各紙・メディアに紹介され
ました。慶大のIBM Qネットワークハブは世界6カ所のハブの1つで、日本の産業界
からはJSR、三菱UFJ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三菱ケミカルが参加し、
慶応大学、IBMとともに量子計算アプリケーションの研究開発に弾みがつきそうで
す。
↓↓↓(プレスリリース)↓↓↓
https://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/53982.wss
◎日本経済新聞 5月17日 慶大が量子計算機の拠点、三菱ケミなど4社が参加
新素材開発などに利用
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30637380X10C18A5000000/
◎時事ドットコム 5月17日 慶大に拠点、化学・金融利用も=米IBMの量子コンピューター
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051701165&g=soc
◎PC Watch 5月17日 慶應義塾大、量子コンピュータ研究拠点「IBM Qネットワークハブ」を開設
~国内企業4社も参画、実問題を解く
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1122433.html
◎Biz/Zine 5月17日 IBMと慶應義塾大学が
量子コンピュータの研究拠点「IBM Qネットワークハブ」開設
https://bizzine.jp/article/detail/2780
◎マイナビニュース 5月17日 量子コンピュータの活用研究を加速-慶大、
「IBM Qネットワークハブ」を開設
https://news.mynavi.jp/article/20180517-ibm_q/
◎日刊工業新聞 5月18日付11面 産学協同で量子アプリ 慶大・米IBMが新組織
最先端商用機使い開発推進
◎化学工業日報 5月18日付 1面 量子コンピューター拠点開所
慶大―IBM 三菱ケミ、JSRが活用
◎Business Insider Japan 5月18日 慶應大の量子コンピューター研究拠点
「IBM Qハブ」が注目の理由
– 量子ネイティブ人材育成、三菱UFJら4社参画
https://www.businessinsider.jp/post-167668
◎ASCII 5月18日 各社の量子ゲート方式量子コンピューターで汎用的に動くソフトを研究開発
慶應矢上キャンパス内に「20量子ビット版IBM Q」へのアクセス拠点
http://ascii.jp/elem/000/001/678/1678729/
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★前号で紹介したグラフェンなど、シート状原子層の自動積層ロボットを開発し
た町田研究室の増渕覚特任講師が日経産業新聞の先端技術面企画記事「次世代の
先導者」欄で紹介されました。もともと原子層積層デバイスの物性研究者である
増渕特任講師がロボット開発に至った動機や、最初の学会で発表した際の反響、
物性研究にとっての意義などが紹介されています。
◎日経産業新聞 5月31日付5面 次世代の先導者
東京大学特任講師 増渕 覚氏(35)
新材料作製、ロボで自動化
時間短縮、本来の研究集中
┌──────────────────────────────────
6【会議紹介】●関連会議・行事を紹介します
└──────────────────────────────────
★9月2日(日)-7日(金)「The 20th International Conference on Molecular
Beam Epitaxy(ICMBE2018)」(@ Renaissance (R) Shanghai Zhongshan Park
Hotel, Changning Road, Changning District, Shanghai, China)
http://mbe2018.csp.escience.cn/dct/page/1
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月9日(日)-12日(水)「日本物理学会秋季大会(物性)」(@)同志社大学・
京田辺キャンパス、京田辺市多々羅都谷)
http://www.jps.or.jp/activities/meetings/index.php
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月9日(日)-13日(木)「2018 International Conference on Solid State
Device and Materials (SSDM 2018)」(@東京大学本郷キャンパス、文京区本郷、
東京都)
http://www.ssdm.jp/
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月9日(日)-14日(金)「2018 43rd International Conference on Infrared,
Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2018)」
http://www.irmmw-thz2018.org/
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月16日(日)-19日(水)「26th International Semiconductor Laser
Conference (ISLC 2018)」(@Hilton Santa Fe Historic Plaza, Santa Fe, New
Mexico)
http://ieee-islc.org/
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月18日(火)-21日(金)「2018年 第79回応用物理学会秋季学術講演会」(@名
古屋国際会議場、名古屋市熱田区)
https://www.jsap.or.jp/jsap-meeting
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
★9月24日(月)-26日(水)「International Conference on Simulation of
Semiconductor Processes and Devices 2018(SISPAD 2018)」(@AT&T Executive
Education, Hotel & Conference Center, Austin, Texas, USA)
http://www.sispad2018.org/
*************************************
■【編集後記】今年は3月ごろから例年に比べ、気温がめっぽう高い日が続き、今夏
の暑さが思いやられます。PIセミナーでも量子情報を取り上げるように、昨今、量
子コンピューター分野の話題が沸騰?しています。それもとくに昨今の計算量ニー
ズの増大などが背景にあるとは思いますが、時代はコンピューターなり、計算技術
の飛躍が求められているからでしょうか。実際にIBM Qネットワークハブのクラウド
経由による応用ソフトの開発にしろ、ImPACTプロジェクトの量子ニューラルネット
ワークのインターネット利用にしろ、大きな話題を集めました。後者については量
子コンピューターの定義をめぐる論争までおまけがつきましたが、要は計算技術の
枠組み脱皮の問題。かつて量子情報というと、息の長い研究分野と認識されていた
かと思います。そのため、過熱しすぎず、ほどほどに話題を集めるというスタンス
であったかと思いますが、今は即、ビジネスに結びつけようという“過熱”の時代に
入ったのか、ここで一考する必要があるのかも知れません。(O)
┌──────────────────────────────────
■発行:東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構
├ http://www.nanoquine.iis.u-tokyo.ac.jp/
└──────────────────────────────────